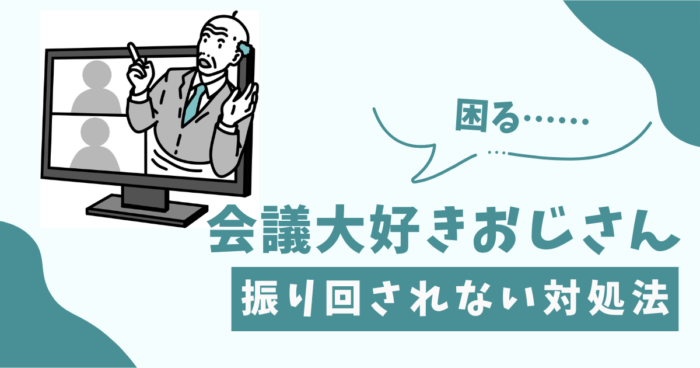ある日の午後、メールに「少しお話できますか?」という通知が来て、胸がひゅっとする。
「お話」と書かれたその一文の奥には、たいてい会議が潜んでいる。
私は何度もこうした会議に呼び出されてきた。
内容は曖昧で、議題はその場で決まる場合もある。
そして90分後、「また別日に詰めましょう」と言われて解散する。
こうした無為な集合を求める存在を、私は「会議大好きおじさん」と呼んでいる。
もちろん女性の場合もいるが、便宜上ここではそう呼ばせていただく。
このおじさん、基本的には善良だ。悪意はない。
むしろ「良かれと思って」動いてくれている。そこがまた厄介である。
会議大好きおじさんの特徴
会議大好きおじさんの主な特徴は、以下。
- 「まず集まりましょう」と言う
- 「一回話そう」が口癖
- 議題はない、あるいは不明確
- 議題よりも、開始時間を先に決めたがる
- 議題は、会議中に話しながら考える
- メールで済む話も口頭で共有したがる
- 参加人数が多いと安心する
- 3人で足りる話に、10人を呼びたがる。
- 古きよき時代の成功譚を、会議の合間に小一時間語る。
彼らに悪気はない。
それどころか「チームで話すことが大事」と、人間関係を潤滑にしようとしているふしすらある。
だが、話すことが目的になってしまっては、議論は霞を掴むようになる。
気がつけば、「話すために時間を空ける」日々が続き、本来の仕事が後回しになる。
会議を頻繁に開く人々を観察するに、彼らはどうやら、「会議を開催している状態」こそが、自己の存在意義であると信じている節がある。
会議大好きおじさんの善意が、生産性を食いつぶす
おじさんたちは「打ち合わせしよう」と言う。
それ自体は、きっと正しいのだ。
会議によって物事が前に進む場面も、たしかにある。
だが、頻度が過ぎると、会議はむしろ逆効果になる。
話し合うことで思考が浅くなり、なんとなく着地する。
「とりあえず集まったから何か決めねば」という空気が、雑な合意を生む。
その結果、「なんとなく決まったもの」が、あとから現場を苦しめる。
とはいえ、敵意を見せるのも得策ではない
会議を減らすべきだ――そうは言っても、真正面から反対すると、
「協調性がない人」になってしまう。
ことにこの国では、「話し合いの輪に加わること」が組織的な美徳とされやすい。
会議大好きおじさんに振り回されないためのマイルドな対処法
そこで、ここからは波風を立てず、しかし確実に会議の負担を減らす いくつかの処世術を紹介したい。
いずれも、私自身が日々の業務のなかで磨いてきた、 ささやかながら有効な対策である。
対策①:事前に「議題」や「目的」を聞いておく
誘われたその瞬間に、「ちなみに今回は、どんな話でしょう?」と尋ねる。
できれば「決めたいこと」まで具体的に聞いておくと、これは本当に会議が必要か? という判断が自他ともに働き始める。
ここで肝要なのは、詰問にならぬよう尋ねることである。
あくまで自然体に、やわらかく。
「議題って、もうありますかね〜?」といった調子で差し出すのがよい。
対策②:先に 「質問を潰しておく」メールを送る
会議が開かれる背景には、「なんとなく不安」「一応聞きたいことがある」など、うっすらとした気配がある。
その気配を、先回りして潰しておく。
たとえば「資料に追記しました」「ここ、少し補足しておきますね」など、チャットで軽く対応しておくだけでも、 「集まらなくても済みそう感が漂い始める。
日々の、ささやかな火消しが重要かも。
対策③:議事録係を買って出る
議事録を書く人間は、会議の主導権を握れる。 全体の流れを整え、要点を拾い、決定事項を明文化する。
さらに言えば、「まとめる視点で会議を見る」ことで、 脱線を察知しやすくなる。
議論が横道に逸れそうなときは、「議事録的には、ここで結論でいいですかね」と切り戻す。
会議という濁流のなかで、静かに舵を切るのだ。
対策④:別のタスクを理由に出席を見送る
理想論を言えば、「その時間、外せない作業がありまして」と言って断るのが一番よい。
だが、実際には難しい。
空気を壊す、という見えない圧がある。
そこで私は、日頃から忙しそうな印象を演出している。
進捗報告をし、カレンダーを小まめに更新し、「今この作業を進めています」という表現を惜しまない。
すると、いざというとき、「あの人は多分無理だな」と先回りして察してもらえる。
対策⑤:(大人数の場合)空気と化し、聞いているフリの練習をする
これは最終手段。
人数が多く、自分に関係する話題がほとんど出てこない会議。しかも断れない。
そういうときは、心を無にして、体だけを会議の場に置く。
リモート会議の場合は、マイクをオフにして、己の気配だけを残す。
うなずいているかのような沈黙と、たまに入る「なるほど…」の小声。
ただし心は、そこにない。
ある種の幽体離脱である。
自分が「会議大好きおじさん」にならないために
さて、私もまた、年齢とともに会議を主催する立場になりつつある。気を抜けば、過去の話に興じてしまいそうになる。
だから最近は、自戒を込めて、会議のたびに以下の三点を反芻している。
- 本当に、この会議は必要か?
- 他の手段では代替できぬのか?
- 参加者全員の時間を奪う価値があるか?
それでもなお必要と感じたときだけ、私は会議の招集をすることにしている。
会議の本質とは何かを忘れてはならぬ
会議そのものが悪いとは、私は思っていない。むしろ、上手に使えば、意見がぶつかり合い、共通認識が生まれ、よき決断が下される、そんな場になる可能性もある。
だがしかし、それは「うまく使えば」の話である。
無目的で惰性の会議を量産し、「集まること」それ自体が目的化してしまったなら、それはもはや時間を焼く行為であり、誰にとっても不幸である。
どうか、会議を文化にしないでほしい。
朝の定例、昼の打ち合わせ、夕刻の振り返り。
会議は、時間という資源を神棚に供えるための儀式。
会議はツールであって、目的ではない。
その前提を忘れぬよう、今日もひとつ、質問を先回りして送る。
それが小さな自衛であり、静かな戦いである。