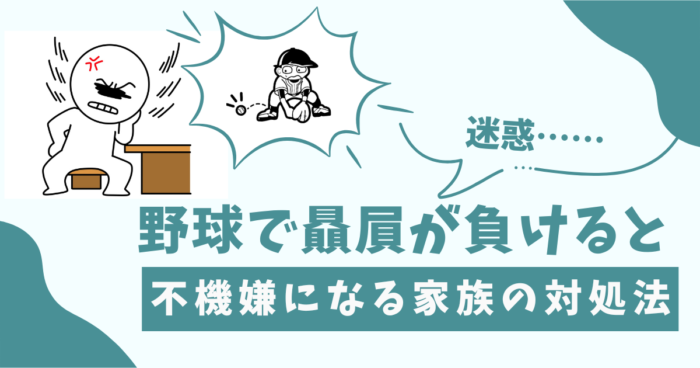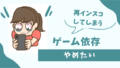野球の試合が終わると、我が家には試合結果と同じくらいの速度で不機嫌な気配が訪れる。贔屓が勝てば饒舌、負ければ沈黙。
筆者はこれを何度も経験してきた。「年間143試合もあるのだ。勝つ日もあれば負ける日もある」と言ってみても、家族はまるで耳を貸さない。
負ければ「もう最悪」と文句の嵐。こちらの心も晴れやかではいられぬ。
最初は不思議だったが、今では天気と同じようなものだと思っている。予報はなく、予防もできず、ただそれをやり過ごす知恵だけを頼りにしている。
けれど、「また始まった」と思うたび、少しずつ疲れてくるのも事実。
ここでは、贔屓の敗北に巻き込まれる無関係な家族の処世術について、静かに書き残しておきたい。
贔屓が負けると、家の空気が沈む
贔屓のチームが点を取られたとき、家の空気が明確に変わるのがわかる。
気温でも湿度でもなく、精神的な気圧配置の問題である。
箸が転がっただけで、場の温度が1度下がる感覚。
贔屓の敗北は、もはや一個人の悲しみではなく、家全体の気分として共有されてしまう。
箸の上げ下ろしで雷が落ちる
「音を立てた」「タイミングが悪い」「目が合った」
理由は何であれ、怒りは突発的に落ちてくる。
食卓でいつもどおり味噌汁を啜っていただけなのに、「うるさいな」と言われたこともある。野球に負けたのは私ではない。箸に罪があるとも思えない。
けれどその怒りは、宛先不明のまま家庭内をさまよう雷のようなものだ。
テレビは消えても、怒気だけ残る
試合が終わっても、家の空気は終わらない。
テレビは消される。リモコンは雑に置かれる。沈黙が部屋の中心に座るようになる。
そして、誰も話さなくなる。言葉よりも先に、怒りの余熱が壁を伝って残っているのがわかる。
「どうして勝てないのか」と聞かれても困る
贔屓のチームは、何故今日負けたのか?――私に聞かれても困る。
監督でもなければ選手の親戚でもない。
「どうしてこんなに弱いんだよ」と言われても、答えは用意されていない。
「昔は強かったんだ」と言われても知らん。生まれていない頃の話をされても困る。
それでも黙っていると、「黙ってるってことは、弱いと認めるんだな?」と詰問される。
これはもう会話ではなく、なにかしらの儀式に近い。
「野球に負けた」のか、「人生に負けた」のか?贔屓のチームが負けると不機嫌になる理由
家族が不機嫌になるとき、試合のスコア以上に、何かが 「崩れている」気配がある。
それは単なる悔しさではなく、もっと根深い何か、たとえば「自分の人生と重ねた怒り」のように思える。
それがわかってくると、ますます扱いが難しくなる。
贔屓と自分の境界が曖昧な人々「負け=自己否定」?
贔屓の負けは、自分の無力さ。采配ミスは、自分の判断力の否定。
チームが負けてキレ散らかしている家族を見ると、そう感じる。
「贔屓チームを応援している」というよりも、もはや「チームと一体化している」に近い。
こうなると、ただの観戦ではなく、試合そのものが自己肯定の試験になってしまう。そりゃあ、負けたときの反動も大きい。
感情移入が強すぎて制御できない
「負けるのは仕方ない。でも、あのエラーは許せない」
そんなセリフを何度聞いたことか。
分析しているように見えて、内心はぐつぐつ煮えたぎっている。感情移入が行きすぎると、理性という鍋の蓋が吹っ飛ぶ。
こぼれた怒りの後始末は、いつも周囲にまわってくる。
怒りの矛先が、やがて家の中に向く
最初は選手に向いていた怒りが、次第に監督へ、審判へ、テレビの解説者へ、
そして最後には、なぜか私にまで及ぶ。
怒りは、放っておくと居場所を探して移動する生き物のようだ。
不幸にも、それが家庭というケージの中で起きる。
ストレスのはけ口が家庭内だけに向く
外で怒るわけにもいかず、SNSで吠えれば炎上し、行き場をなくした情熱は、一番安全な場所=家庭に向けられる。
でもその「安全な場所」にいる者にとっては、まるで地雷原を歩くような日々である。爆発が起きないことを祈りながら、次の試合日を確認する。
野球で不機嫌になる家族へのNG対応【逆効果】
機嫌の悪い人に「機嫌直して」と言えば、たいてい逆効果だ。ましてや野球の敗戦が原因となると、下手に踏み込むと延長戦が始まる。
こちらはもう試合終了のつもりでも、相手の心のイニングは続いている。
ここでは、野球観戦で不機嫌になっている家族に対し、やってはいけない対応について、いくつか書いておく。
「たかが試合でしょ?」は禁句
この一言で、3ラン級の怒りを買った人を何人も知っている。
「たかが」は、相手の価値観を踏みにじる言葉だ。
こちらに悪気がなくても、それは「信仰への冒涜」に近い受け取られ方をする。
野球の贔屓チームというのは、そういう扱いなのだ。
勝手に励ます・慰めるのも逆効果
「明日も試合があるよ」「切り替えてこ!」
それは自分が落ち込んだときに言われて嬉しい言葉か?
怒りの底には、まだ「悔しがる余熱」が残っている。そこに水をかけると、かえって蒸気が上がる。
励ましは、タイミングを誤ると火傷のもとだ。
「また怒ってるの?」と上から目線になる
口に出す前に思い出してほしい。その怒りは、たぶん昨日も見た。おとといも、去年も。
でも「また」という言葉に、人は過去をすべて否定されたような気になる。
繰り返しているのは事実かもしれないが、怒っている本人にとっては、今日が 「本番」である。
野球で不機嫌になる家族を沈める知恵7つ
野球は9回で終わっても、家の険悪ムードは延長戦に突入しがちだ。
早く風呂に入って寝てくれればよいのだが、そううまくはいかない。
ここでは、こちらの消耗を最小限にしつつ、相手の火種を鎮火させる方法について、いくつか紹介したい。
効果のほどは天候や相手の機嫌によるが、試してみる価値はある。
台所に立つふりをして、戦場から離脱する
一番かしこいのは、「そこにいないこと」だ。
野球談義が始まりそうなら、「ちょっと台所で洗い物あるから」「あ、風呂沸いた」と言って離れる。
相手の怒りの矛先が見えないところに自分を移せば、当たらずにすむ。
「なるほど」と一言だけ言っておく
意見も反論もいらない。ただ「なるほど」と言う。
それだけで、なぜか話が続かなくなることがある。
肯定でも否定でもない、日本語の曖昧なバリアは、こういう場面にこそ有効だ。
もちろん、棒読みにならないように。怒りのセンサーは、意外と敏感である。
語らせて、熱が冷めるのを待つ
誰かに怒りを聞いてほしいだけ、というときもある。
うなずきながら聞いていれば、そのうち相手が疲れて黙る。
途中で茶を出すと、怒りが弱火になることもある。
ただし、「それは違う」などと言ってはならない。それは油を鍋に注ぐような行為である。
あちらが沈黙するなら、こちらも静けさで応える
黙っている相手に「なんで黙ってるの?」と言えば、爆発のスイッチになる。
沈黙には、沈黙で返すのがよい。
ただし、敵意のある無言ではなく、 「同じ空気の住人」としての無言が肝心だ。
湯気の立たない時間を、ただ一緒に過ごす。
怒りとは、ときに何もせずにやり過ごすのが正解である。
感情を「物」に移してもらう
こちらから「ペットボトルでも潰してみたら?」と提案するのも一手。
物理的な発散は、感情の毒抜きとして有効である。
できれば壊しても問題のないものを選んでほしい。
「プロっぽく扱う」ことで気を鎮める
怒っている家族に対し、「監督目線ではどうなんですか?」と聞いてみる。
「今日は中継ぎの出しどころが難しかったですね」など、あえて 「戦術家」として扱う。
すると、本人は急に語りだす。
評論家としての自分にスイッチが入れば、怒りではなく知識の披露になる。
そのまま野球談義モードに移行すれば、機嫌の回復も見込める。
最終手段:こちらが逆ギレしてみせる
どうしても相手の怒りが収まらないときは、家族にではなく「試合内容」に対してこちらから逆ギレしてみるのもアリだ。
「なんや! あのヘボ送球!」と、間髪入れずに大声でツッコミを入れる。
「ファールやろ! 今の!」「継投が遅いわ!」と、あえてこちらが「相手よりもっと怒っている存在」を演じてしまうのだ。
人は、自分よりも強烈に怒っている相手を見ると、意外に冷静になる。
この逆ギレは、あくまで「怒りの分散」として使う技なので、ある程度は「演技」で構わない。
これがうまく決まれば、場の空気がふっと変わることも多い。
ただし、乱用は禁物。
この手段は、あくまでも最終回のサヨナラホームランとして取っておくべきである。
文句ばかり言っている大人は、みっともないからです。はい。
どうしてもつらいときの 「自分の心の守り方」
対処してもダメなときはある。
そんなときは、「どう乗り切るか」ではなく、「どう守るか」が大切になる。
怒りに巻き込まれない距離のとり方、心の境界線の引き方について考えてみたい。
家族であっても、べったり付き合わねばならない理由など、どこにもない。
怒っている人には、つきあわなくてよい。
これは冷たいわけでも、無関心でもない。怒りはその人のものであり、こちらが引き取る筋合いはないのだ。
とはいえ、家の中という密室で暮らしていれば、逃げ道も限られる。
だからこそ、「自分を守る知恵」も道具箱に入れておく必要がある。
不機嫌は相手の責任と割り切る
「また怒ってる」「機嫌をとらなきゃ」などと思い始めると、こちらが勝手にお世話係になってしまう。
けれど本来、相手の機嫌は、相手の持ち物だ。
自分のものを、他人に持たせてはいけないし、持たされてもいけない。
「この人は、いま勝手に荒れている」――そう割り切るだけで、心の消耗は減る。
物理的に距離を取る(別室・外出など)
怒りが物理的に近いと、空気ごとこちらに移ってくる。それならば、離れればいい。
別室に行くもよし、ちょっと散歩に出るもよし。
「買い物行ってくるね」など、何でも理由をつけて外に出れば、怒りが薄められていく。
【余談】勝っても文句、負けても文句、これは一体何事か
驚いたことに、私の家族は、勝った試合でさえ文句をつける。
「点数が多すぎて緊張感がない」「ジグザグ打線はいまどきどうなの」などと、聞いているこちらが疲れてしまう。
勝敗は二の次で、ただただ不満を漏らすことが目的なのかもしれぬ。
最後に:野球は9回まで。不機嫌は延長しないように
野球は人を熱くさせる。
だがその熱が家族を疲弊させるなら、少し冷まし方を考えてもよいのではないか。
不機嫌になる自由もあれば、それに付き合わない自由もある。
怒りに巻き込まれないという選択は、立派な大人の知恵である。
なるべく心を守って、今日の試合は今日のうちに、終わらせてしまおう。どうせ、家族はそれでも懲りずに、翌日もまた試合を見るのだから。
延長戦は、球場だけで充分だ。